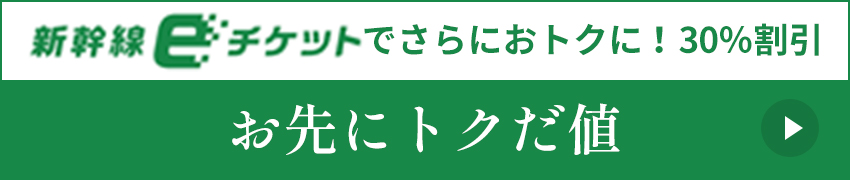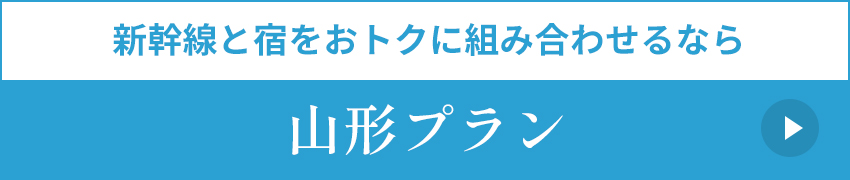羽黒山周辺の
寄り道スポット
山伏が味わった精進料理
日本人にとって山とは、神の宿る聖域そして祖霊が静まって子孫を見守る場所だった。
山の神霊をわが身に宿す修行を重ねた山伏たちの「食」を支えた精進料理を、羽黒修験道の聖地・
羽黒山で味わってみよう。
杉の巨木に囲まれて
羽黒山の麓にある随神門から、樹齢300年を超える杉並木の中を三神合祭殿まで2446段の石段が続く。夏でもひんやりした風が通る、静かで穏やかな空間は「神」の存在を感じさせてくれる。三神合祭殿の近く、杉の巨木に囲まれて建つ建物が「斎館」。霧に囲まれた重厚な建物で江戸時代中期の元禄時代に寺院として建てられた、山伏たちが住んでいた遺構だ。現在は参拝客の宿泊所、食事処として活用されている。

山菜が主役の精進料理
精進料理とは一般的に、仏教の戒律に基づいて肉や魚を使わず、野菜や穀物、豆類などの植物性食材を主に使用した料理のことをいう。出羽三山ではその季節に取れた多種多様な山菜が主な食材。何も取れない時期は乾燥や塩蔵などで保存しておいたものを使う。体調に合わせ、薬効のある食材を用いることもある。料理の一つ一つにさまざまな技が用いられ、口に含むと体全体が浄化されるようなすがすがしい気分になることができる。

進化を続ける伝統の味
「精進料理に決まったレシピは何一つありません。口伝で技法を伝える一方、新しい調理法も取り入れています」。料理長の伊藤新吉さんが語る。山菜には「あく」と呼ばれる独特の苦味があり、そのままでは食べられないものがある。それを何とか食べられるようにする下処理が「あく抜き」。先人が試行錯誤の末に確立した技法だ。時代の変化で使える技法が増え、使えるものは積極的に導入。伝統の中にも常に進化を続けている。

世界の人たちが味わう
精進料理に対する関心が高まっている。ここ数年は若い女性や外国人の客が増えているといい、「体にいいものを求めるヘルシー志向にマッチしているのでは」と伊藤料理長は分析する。ベジタリアンやヴィーガンといった食のスタイルや、イスラム文化圏の人向けにハラールへの対応も可能。「外国の方は、以前は苦手そうなものには手をつけませんでしたが、今は恐る恐る口に入れてみて、結局全部召し上がる方が多い」のだという。

神仏習合の名残
羽黒修験道は、日本の神道と仏教が融合して一つの信仰体系となった「神仏習合」の形を取っていた。明治時代に出された神仏分離令で神社と寺院が厳格に分離され、出羽三山は「神社」とされたのを機に、山内にあった仏閣の多くが破壊された。斎館内の「羽黒三所大権現」の扁額は神仏習合の時代の名残。神殿の近くにお寺を表す「卍」の印があったりするのが興味深い。

日本人が抱き続けてきた、山に対する敬虔(けいけん)な気持ちが、出羽三山には今も息づいている。それを「食」の形で表したのが精進料理といえる。動物性の食材を使わずとも十分な満足感を与えてくれるのは、その敬虔な気持ち故ではないだろうか。
この記事を見て来館いただいた方に
出羽三山クリアファイルをプレゼント!