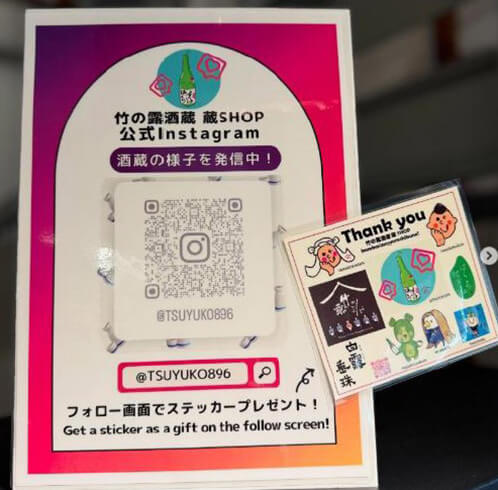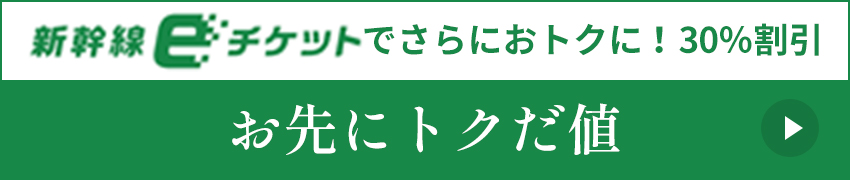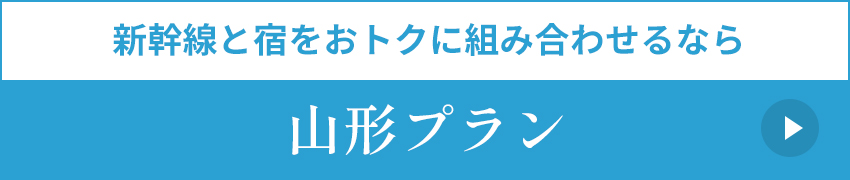羽黒山周辺の
寄り道スポット
「地元産」にこだわった、
味比べが楽しい真の地酒蔵
米どころ庄内では日本酒づくりが盛ん。各地にある酒蔵が競い合って個性的な味わいを醸し出している。
月山由来の水、地元産の米を用いて地元の人がつくる「真の地酒蔵」を訪ねた。
月山の麓、出羽三山神社に通じる道にも近い「竹の露酒造場」は1858年の創業。冬は蒸気が上がる中を蔵人たちが忙しく動き回るが、夏場は静かな雰囲気だ。歴史を感じさせる「1号蔵」は羽黒山随神門前にあった建物を移築したもので、約370年の時を経ている。出羽三山神社の御神酒(おみき)はかつて宿坊で作っていて、一番いい酒を醸す坊を建物ごと持ってきたのだという。酒の味を左右する「蔵付き酵母」が独特の味わいを生みだしている

米、水、人、神、全て地元のものでつくっている酒蔵です」。代表の相沢(あいさわ)こづえさんが語る。原料の米は全部鶴岡市産。それを醸す蔵人も全員が蔵の近くに住んでいる。蔵に何かあった際もすぐに駆け付けられるように、との意味があるのだという。1号蔵の一部を改装した「蔵SHOP」には「白露垂珠」など同社の酒のほか、酒粕を用いたオリジナルのスイーツ、酒に関するグッズなどが並ぶ。

蔵SHOPの一角には有料試飲コーナーがあり、興味のある酒を味わってみることができる。米や精米歩合、製法などの違いでいろいろなキャラクターがあるが、フルーツのような柔らかい香りと柔らかな口当たり、すっきりした後味が印象に残る。食中酒に合いそうだ。山形県内で開発された酒造好適米「雪女神」で全国新酒鑑評会金賞を獲得するなど、技術力の高さは折り紙付き。「地元の素材でさらに上を目指したい」と相沢さんは意欲を見せる。

蔵SHOPの2階はイベントスペース。記念撮影ができるコーナーもある。光沢を放つ太い木材が歴史を感じさせる。柱の配置が神社の鳥居のようになっているのも、宿坊だった頃の名残かもしれない。

酒造りで大切な仕込み水は、地下300メートルからくみ上げた「月山深層無菌高水素シリカ波動超軟水」。口の中に広がる優しい味わいは酒のキャラクターとも通じる。コラーゲンの構成を助ける成分「シリカ」を多く含むことから「美肌の水」としても知られ、メディアで取り上げられたこともあるという。生水のまま瓶詰めしてショップで販売している。

銘柄ごとに個性があり、飲んでおいしいのが山形県の酒の特徴。酒蔵を訪れ、酒にまつわるストーリーを知った上で味わえば、より深く印象に残ることうけあいだ。
蔵shopに来ていただき、インスタフォローいただいた方に竹の露のオリジナルゆるキャラが大集合のかわいいシールをプレゼント。