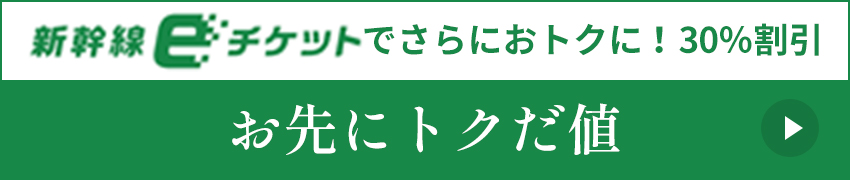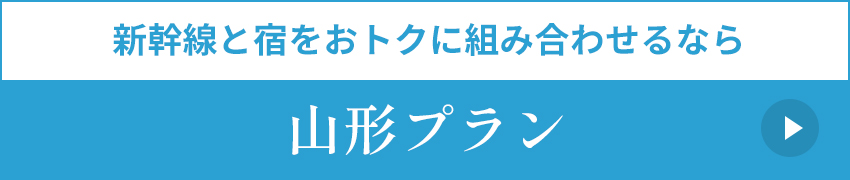羽黒山周辺の
寄り道スポット
旧庄内藩士たちが
切り開いた松ヶ岡
時は明治維新。新政府と江戸幕府が戦った戊辰戦争で庄内藩は幕府側につき、降伏。職を失った庄内藩士たちが開墾に取り組んだのが「松ヶ岡」だ。養蚕で「賊軍(ぞくぐん)」の汚名をそそごうとした奮闘の跡が往時を物語る。
戊辰戦争で敗れ、職を失った庄内藩士たち約3000人が、新たな産業を興そうと刀をくわに持ち替え、開墾に取り組んだ地が「松ヶ岡」。荒れ地を広大な桑畑にし、木造3階建て10棟からなる国内最大の蚕室群を建設して養蚕に取り組んだ。蚕室のうち5棟と、開墾事業の拠点となった「松ヶ岡本陣」、蚕業稲荷神社などが現存し、「松ヶ岡開墾場」として国指定史跡となっている。ワイナリー「ピノ・コッリーナ」も近い。

木材や屋根瓦など蚕室の部材の一部は、廃藩置県に伴い解体された鶴ヶ岡城からこの地に運ばれ活用されたものだという。現在までたびたび地震が起きているが、それにも耐えて風格ある姿を今に伝えている。現在も実際にカイコが飼われているほか、養蚕に特化した建物の構造を見学することもできる。

一番蚕室は「松ヶ岡開墾記念館」として、開墾や養蚕に関する資料を展示しており、松ヶ岡とシルクの歴史を実感することができる。また全国の土人形や土鈴のコレクションもあり、愛嬌(あいきょう)のある姿が見る人の心を和ませてくれる。

戊辰戦争で降伏した庄内藩を寛大な処分にするよう指示し、開墾による地域再興を助言したのが西郷隆盛だった。これをきっかけに旧庄内藩士が西郷の下で学ぶようになり、西郷の教えを「南洲翁遺訓(なんしゅうおういくん)」として刊行し全国に広めた。西郷をまつった南洲神社が九州以外では唯一、酒田市にあるが、それも西郷と庄内の深いつながりを物語る。記念館には西郷に関する資料も展示されている。

蚕室が建つ一帯は緑が多く、青空の下を吹き抜ける風が心地よい。桜並木は春の花見スポットとして人気。静かな雰囲気は、ここだけ時間が止まったような感覚だ。

明治時代、仕事を失った武士による開拓が各地で行われたが、松ヶ岡は数少ない成功例だ。松ヶ岡では後に稲作や果樹が導入され、最近ではワイン用ブドウや小麦の栽培が試みられている。挑戦の物語は時代を超え続く。